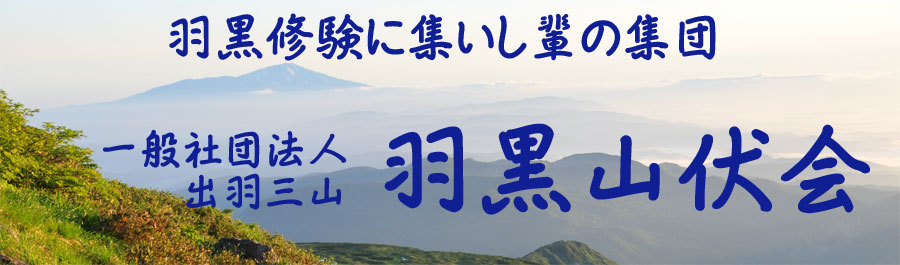
平成18年8月10日
出羽三山神社 新三山抖擻行「出羽三山≪順峰・逆峰≫大回峰行」
|
|
||||
|
羽黒山「随神門」↓ 表参道「祓川」↓ 表参道杉並木 ↓ |
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
出羽三山「月山」頂上 ↑ |
月山登拝道 ↑ 湯殿山大鳥居と参籠所 ↑ |
|||
|
羽黒派古修験道≪秋の峰≫
先達山伏 田代貢晴
娑婆在所 山形県酒田市宮野浦1-14-11
私的体験!
◎山岳修験の御山の月山、羽黒山、湯殿山の御神域を巡る≪三山抖擻行≫を今に再現する。
※抖擻行=険しい峰々に分け入り、一心不乱に駈けて、己が煩悩を滅却する厳修行
◎その日時を平成18年7月27日の午前零時と定め、羽黒山随神門より単独で出立する。
◎「出羽三山≪順峰・逆峰≫大回峰行」と私的に称して往路と復路の全行程を抖擻する。
順峰行程 羽黒山随神門→御坂→三神合祭殿→吹越→月山高原ライン→八合目中之宮→
九合目→月山本宮→牛首→月光沢→湯殿山本宮
逆峰行程 湯殿山本宮→月光沢→牛首→月山本宮→九合目→八合目中之宮→
月山高原ライン→吹越→三神合祭殿→御坂→羽黒山随神門
◎道程は、往路七里、復路七里と見込み、その所要時間は昼夜兼行二十時間以内と目論む。
◎装束は白衣、白袴、太多須嬉、脚絆、地下足袋、金剛杖、神鈴、菅笠を着用し帯用する。
◎天気情報(平地) 天気=晴れ 気温=26/20 湿度=55% 風向=西北西/風速=4m/s
≪私的体験!備忘録(平成18年8月5日)≫
7月26日 予定より早く、午後11時40分に羽黒山随神門を出立する。
①修験装束の清浄な白の上衣と袴を着ける。羽黒派古修験道「秋の峰」入峰度位の証の太多須嬉を首から下げて、袴の右腰帯に御神鈴を絡める。脛に白脚絆を巻き白地下足袋を履いて足拵える。額を汗止めタオルで縛り、其の上に乗せた菅笠に防虫ネットを被せ垂らして顔面全体を覆う。数分前の俄雨は梅雨前線の急接近か?この用心にと、白のパーカーで背負うミニリック絡みの全身を包み込む。左手に険しい山野を突き奮う金剛杖を握り、右手に懐中電灯一本を持って漆黒の表参道を照らし始めれば、私の心身の緊張感は最高潮に満ちて、愈々と出立することにした。
②漆黒の御坂に勇んで駈け入れば、参道全体には濃い霧が垂れ籠めていた。参道に敷き
詰められた平石を踏む足元は見え難く、表面は水滴で濡れている。地下足袋の足元を
滑り取られないようにと、一段一段の足運びに注意を払いながら石段を踏み上がる。
③胸突き八丁の「三の坂」に踏み上がれば、霧は一段と濃く漂い、身体全体を覆い隠すよう。この濃さを大袈裟に言えば、庭の水撒きホースのノズルを噴霧に切り替えて水を撒いたと同様に掛けた眼鏡のレンズを一瞬に曇らせてしまう。石段を進む足元は殆んど見えない。幾度も眼鏡のレンズを拭こうと立ち止まるが、その甲斐も無くて、遂には眼鏡を外してしまった。周囲を覆う漆黒の闇と濃く漂う霧の視界不良のままに、裸眼の視力不足を重ね合わせてしまう。この悪条件を無理押しに「三の坂」の石段を踏み上がれば、それを外して転倒するなどの大怪我の元になる。一歩一歩に注意を更に重ね合わせて石段を踏み上がって行く。
④其処から進んで数分も経ない内に、急に、懐中電灯の明かりが橙色に変化してきた。
怪訝だぁ?電池の消耗にしては早過ぎる!霊的な何か尋常ではない兆しかも?と五感
を鋭く澄ます!が、この判断もし兼ねて。今、この漆黒を貫く唯一の明かりを失って
は如何にも行かぬ!多分に、買置き電池の自然消耗と濃い霧の水滴とが相俟って電池容量を損なった減光であろう!と心の整理を急いた。そして、この「三の坂」を越えれば行き着く「羽黒山頂」で新しい電池に入れ替えれば良いとした。果たして、この一回分の入れ替え電池だけで漆黒を貫く抖擻行をし終えることが出来るのか、心許もなくて。
7月27日 午前00時13分に「羽黒山頂三神合祭殿」前に立つ。
午前00時30分に「吹越堂」前を通過して月山高原ラインを一路月山へと進む。
こんな深夜に何処に向かうのか?乗用車二台が私の背後に迫り、大きなエンジン音を響
かせて走り抜けて行く。
午前1時24分に一合目「海道坂(かいどうざか)」を通過する。
午前1時56分に二合目「大満(だいまん)」を通過する。
①明らかに月山八合目に向かうのだろう、軽ワゴン車一台が漆黒の潅木端を歩く私の側
を通り過ぎて行った。こんな漆黒の闇を歩く人に遭遇する等と想像もし得ない中で、車のライトに照らされて急に白装束の私の姿が浮かび上がる様は、誰にとっても異様に映る他はなく、その吃驚している様子が車の窓越しに強く感じたのである。漆黒の闇を独り黙して歩いている私にしてみれば、その孤独に苛む心が高じていたのも正直なところであった。こうした矢先に通過した軽ワゴン車であったことから、この車を運転している人には俄かな親近感を覚えてしまって、「第一登拝者発見?!」と、諧謔心が瞬間的に溢れたのであったが。然し、先方の、あの度吃驚の様子を思えば、その気騒がしの因は全て私に間違いもなくて、何とも申し訳ない気持ちにもなったのだと。
②後に、このワゴン車を運転していた方とは、私が月山頂上に差掛かった時に、「麓から
歩いて登って来たのは貴方でしょう!」と声を掛けられた。私も「あの時の軽ワゴン
車の方でしたか!」と掛け返した。お互いに上り下りする動作に得も言えぬ好奇の微
笑を重ね合わせながら。
午前2時20分に三合目「神子石(みこいし)」を通過する。
午前2時31分に四合目の「強清水(ごわしみず)」を通過する。
午前3時03分に五合目の「狩篭(かりごめ)」を通過する。
午前3時24分に六合目の「平清水(ひらしみず)」を通過する。
参籠所にご奉仕する出羽三山神社の職員か?それとも登拝者か?5台の車両が続け様に白む月山高原ラインの急坂をフルアクセルにマフラーを震わせながら過ぎ去った。
午前3時59分に七合目の「合清水(ごうしみず)」を通過する。
長く感じるほどに登り歩けども七合目札が見つからない。見逃したかなぁ?!と不安感
が先走ったが、それからも随分と歩いて漸く確認することができた。
午前4時25分に八合目の大駐車場に到着する。
大駐車場には十台に満たない乗用車が駐車している。早朝の登拝を目指す大型バス一台
が今到着した。直ぐに下車してくる講の袢纏を着た方々は何処から詣でた講社なのか?
集まり出した、その前を通り過ぎようとすると、老若男女、数十人の一瞥がきた。
午前4時36分に八合目「中之宮御田原参篭所」に到着する。
①歩き始めてから約5時間、頂上方向を見上げる野外のベンチに初めて腰を下ろして暫
時休息することにした。段張(食事=山伏言葉)用にリックに詰め込んできたアンパン三個と餡餅を二個、そしてクッキーの包み紙を引き破って頬張る。交互にアンパンと餡餅とクッキーを食い気露わに頬張り続けて、一気にスポーツドリンクで萎んだお腹に流し込めば一心地にと。
②中之宮奉行ご奉仕の太谷権禰宜、参籠所ご奉仕の職員の方々からは、強行な抖擻で引
き起こされるスポーツ障害防止へのアドバイスを頂戴する。
午前5時00分に月山頂上を目指して出立する。
午前5時45分に九合目「仏生池」前を通過する。
午前6時25分に月山頂上に立ち「月山本宮」を参拝する。
月山奉行阿部禰宜と大江権禰宜と暫し語らい、御神酒を頂戴して「まことに有難い! 」。
午前6時45分に湯殿山へと下る。
午前8時25分に湯殿山に到着して「湯殿山本宮」を参拝する。
御本宮ご奉仕の灘波権禰宜、大川権禰宜と暫し語らい、足湯に浸かって休息を得る。
● ≪順峰≫道程計測「歩行数42.048歩」・「歩行距離数29.43k」「歩行時間9時間5分」
午前9時15分に逆峰達成を目指して月山頂上に向け、湯殿山を出立する。
御本宮祓い場ご奉仕の大川権禰宜と他の職員の見送りを受ける。
午前9時50分に「薬湯小屋」前を通過して、その嶺上の湧き水場にて休息する。
何時時の段張分になるのか、アンパン三個、餡餅二個、クッキーを頬張る。甘すぎた食
料だけの持参を嘆いて梅干一個の塩辛さの旨味を口惜しく思う。こうして修験者の験力(修行で獲得した神力)の低俗性を剥き出しにする。リックに掛けた空の水筒に大自然の冷たい湧水を注ぎ満たして抖擻行をし終えるまでの飲料水を得た、一安心だと。
午前10時25分に月山頂上へと出立する。
①途中では、峰中の前斧役であった叶さんが先達する小中学生?の三十人位の集団、現
斧役で法螺役に昇進したばかりの勝木さんが先達する十数名の集団と擦れ違い、挨拶
を交わす。それからも数名、数十名単位の登拝集団の幾組かと擦れ違う。その中に、
一千四百数十年と連綿に厳修されてきた羽黒派古修験道「秋の峰」に峰入する度衆輩の二名を見付けては、八月末の羽黒山中「吹越籠堂」での再会を確約し合う。
②心身の疲労も極度に蓄積されてきて月山の牛首を登りきる苦しさは想像以上になる。
胸突き八丁を絶え耐えの息のままに一歩一歩を運ぶが、暫し立ち止まっては溜息交じ
りに頂上付近を見上げるばかりになってきた。早朝にはガスが頂上付近まで流れ込ん
でいたが、その後の好天が幸いして眺望は開けている。この見晴らしの良さは心身の
疲労を癒し、爽やかに流れる風は火照った身体を冷やす心地良さの快感だと。
午前11時58分に「月山頂上」に立つ。
午後0時15分に月山山頂を出立して「羽黒山」へと一路下る。
午後1時29分に八合目「中之宮参篭所」に到着する。
①中之宮参籠所にご奉仕の、峰中の新斧役に就任したばかりの早坂さんと他の職員より、高原ラインのアスファルト道路の表面が日射で熱くなっているだろうから、その輻射熱に対する体調の障害防止には水分補給が欠かせないとのアドバイスを頂戴する。私の体調の心身疲労の蓄積は十分に自覚しつつも、幸いに、抖擻への挑戦意欲は未だに衰えては居ない。この意欲に任せるままに下る先を急ぐことにした。
②三合目あたりから二合目に差掛かる抖擻の時間が物凄く長く感じた。一つカーブを越えどもまたカーブ、行けども行けどもまたカーブの連続で、中々と羽黒山の山容を望める処までは行き着けないのである。疲労の蓄積も極限に近くなってきた。身体全体の動きが重石を背負った如く鈍重になっている。こうした体調が災いして幻覚の長い距離感覚を生み出させてしまのか?然し、此処まで下って来れば、予定の道程の三分の二位は抖擻をし終えたであろう。何とかと、このままに歩き続けて抖擻行をし終えることができれば修験者冥利に尽きる。「終着点の随神門を潜る!」この大感激だけをイメージしながら金剛杖を頼りに一歩一歩を運ぶが肝心だと、己に幾度も言い聞かせる有様に。
③然し、未だ、羽黒山の山容が見えて来ない!日が落ちる前に辿り着けるのか?こんな心の焦りが休息への欲望を萎ませてしまう。これに更に追い打つのか?!実際に休息したくとも、「しゃがむ姿勢」を取ることが出来なくなったのだ。十数時間の抖擻の行程を、殆んど休憩を取らずに直立姿勢の速歩のままに進んできた私の肉体は、既に疲労困憊に打ちのめされている。「しゃがむ姿勢をとる」などと、自力で腰を曲げるのも困難なほどに痛み切っている。特に大腿部や脹脛の筋肉は硬直していて、時折に激しい痙攣が襲ってくるのだ。こんな極度の筋肉疲労が引き起こす痙攣の苦痛に喘ぎながらの得心は、このままに歩き続けて痙攣している筋肉自体を解すと言う、この荒療治が最良であろうと言うことである。これが功を奏したのか?何時の間にか、幾度も襲う痙攣が少しは治まってきたのである。
④逆峰の行程の八合目を下る月山高原観光ラインでは、ラインを上って御田原参籠所に戻るご奉仕の出羽三山神社の職員や、下って出羽三山神社に帰る職員が運転する車両も通り掛っては励ましの声を掛けてくれた。また観光ラインをワンボックスカーで上る峰中輩にも偶然お会いして励まされた。そして通り過ぎる定期バスの運転手や、月山の登拝時に何処かで擦れ違った方々であろう?下る観光バスの観光客の方々からも窓越しに大きく手を振られて励まされた。こうした沢山の方々からの励ましを受けて、「この回峰行を是非にとも達成しなければならぬ!」と疲労困憊の極みに折れて壊れそうな心の持ち様を立て直す。
⑤羽黒山麓が近づくにつれてブナ林を抜く風が無くなってきた。日当たりの良い道路表面のアスファルトの輻射熱を厳しく感じるようにもなって来た。
⑥漸く羽黒山頂に到着する。今日の店仕舞い中の土産品店「さいとう」の店主ご夫婦は知己である。お二人の目にも疲労困憊の私の姿が異様に映って留まったのであろう。目敏く私を見つけては労りの声を掛けてくれた。「回峰行をし終える直前だ!」と、か細い声で答えることができた。
午後6時14分に羽黒山随神門を潜り、逆峰をし終える。
①息も絶え耐えに待ち望んだ随神門を潜る。「やったぁー」と呻きに似た言葉を腹の底 から絞る。齢57歳の肉体は如何にか持ち堪えた。地下足袋のコハゼを抜く動作にも、腰を屈める苦痛に口を歪めて間合いを掛け過ぎる余力の無さではあったが、呻き声に似た安堵の息吹は吐き出せた。天候も、未明から早朝に掛けては出羽三山全体を覆う濃い霧に見舞われてしまったが、その後の天気は好天に転じて万事が幸いであった。擦れ違う方々からの励ましも沢山頂戴して本当に有難かった。こうして全てに恵まれて成し得た大回峰行であったことよと。
②摂取した段張食料は、餡餅12個にアンパン6個とクッキー一袋である。摂取の水分は、
スポーツドリンク1.5ℓ、コーヒー500ml、湧き水500 ml、の計2.5ℓ。抖擻行前後の
体重の増減は3k減。不明に嘆くは梅干の持参の無きことよと。
③自宅に帰り着いて今に思えば、抖擻行自体を途中で断念させる膝や足首の主要部位がスポーツ障害に襲われることもなくて幸いであった。終えて三日間ほどは、極度の疲労による倦怠感や筋肉痛に襲われて、特に立ち上がる動作に呻き声を上げる生活が続いた。寝床から起き上がるにも柱や壁を縋って這い上がる始末であったのである。部屋からの移動も同様に、壁を伝って全身を屈めながら蟹が歩く様に横歩きをする。身体障害時の移動の困難性を始めて体験したことにもなった。然し、こうした状態も、一日、二日と、日を置くごとに和らいで、四日目頃からは普通の体調に戻ってきた。軽いウォーキングをし始めようとする意欲が湧いてきたのである。自宅周囲の、マイコースに一歩を踏み出してみれば、身体全体の硬直した筋肉が程よく解れて、抖擻前の心身の軽快感が戻ってきたのである。大感激であった。
④こうした心身を維持できるのも、生活習慣のウォーキングの運動成果であろう。古くの湊町酒田市街の光景は、北に出羽富士と称する霊峰鳥海山。その東南には修験の世界を秘して険しい月山の山容を望む。日本屈指のこの二つの霊山の裾野を横に結び束ねる様は山形の母なる大河の最上川。この悠久の流れを西の日本海に急いて注ぐ土手沿いを、お天気任せに暢気に構えながら早朝に歩き始める。其の延長の日本海砂丘の松林に明媚に建つ土門拳美術館、この高台の酒田市立美術館と公益文科大学周辺の散策コースを進んで行けば、約10キロのマイコースになる。日和の良い清々しい早朝に、このコースを速足で歩き、同時に「神拝詞(祓詞・三語・三山拝詞・三山祝辞・大祓詞・十種祓詞・ひふみの祓詞・十種神宝大御名・神拝詞・稱言・禊祓行事・鎮魂行事、等の神詞)」を腹式呼吸法で唱えて歩めば有酸素運動のウォーキング時間は瞬く間に一時間以上が過ぎていく。途中で行うストレッチング運動の、スクワット運動や腹筋運動にレッグレイズと腕立て伏せ等のメニューを幾セットか重ねて行えば、約一時間四十五分位の運動の生活習慣になるのである。継続したこの自己流の心身鍛錬法の爽快な汗の賜物が、大回峰行と私的に称して挑戦した苦難の三山抖擻行を達成させ得たのである。また、険しい山野を一心不乱に駈けて貫く体力強化の効果性も証明できたのである。こうした健康的な体力増進の喜びは、今は高齢化社会の「健康貯金」とも称されて、何物にも代え難い私の貴重な財産になっている。
⑤更に、私の隠れた「健康貯金」の源泉に、30年歴になる「珈琲嗜好」の生活習慣が有ることも付け加えたい。朝から夜までの一日に、約二リットルを飲み干すドリップしたブラックコーヒーの美味さは格別である。昨今のインターネット上に公開されている医学情報や健康情報に由れば、楽しみながら飲む珈琲の秘めた成分が、健康維持には著しい効果を発揮していると言う。代表される成人病の、特に高血圧症や高脂血症に糖尿病と心臓病等の予防には抜群の効能があるとして、珈琲嗜好者の大朗報ともなった。珈琲を喫する楽しみの生活習慣が、同時に自分自身の健康貯金の源泉にもなっている。こうした健康的生活の善循環が、今後の私の人生にも珈琲色の深みとコクを増していくことは間違も無くて。
●≪逆峰≫の道程計測「歩行数46.065歩」・「歩行距離数32.24k」「歩行時間9時間29分」
●三山回峰行≪順峰・逆峰≫の総道程計測
「歩行総数88.113歩」「歩行距離総数61.67k」「歩行総時間(休憩を含む)18時間34分」